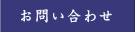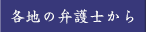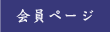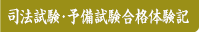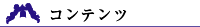明治大学法曹会 司法試験合格体験記
関澤駿輔
2024年 明治大学法学部4年
Ⅰ 経歴
2021年3月 私立川越東高等学校 卒業
2021年4月 明治大学法学部法律学科 入学
2025年2月 令和6年度予備試験最終合格
2025年3月 明治大学法学部法律学科 卒業見込
Ⅱ 予備試験志望の動機
私は、大学3年次の法学部・法制研究所共催の予備試験対策ゼミ担当だった藤瀬淳先生から、今の段階であれば法科大学院進学を第一に目標にするよりも予備試験を目標にした方が良いというご助言をいただいたことをきっかけに、予備試験を本格的に志望するようになりました。
入学当初は法曹と一般就活(マスコミ系を漠然と志望していた)のどちらかに進みたいなと考えていました。法曹に進むとしても、法科大学院進学を念頭にしていました。大学1年次の10月頃から、憲民刑入門講座を取り、倍速で視聴し始めました(コロナの影響があり、オンラインでした)。ただ、復習もせず倍速で聞き流していただけだったので、あまり身についた印象はありません。
ただ、大学3年次に上記のゼミでご助言をいただき、「予備試験の勉強をしていれば、同時に法科大学院の勉強にもなるだろう」と考えるようになり、予備試験の勉強をしてみようと思うようになりました。
Ⅲ 予備試験短答式の勉強方法
予備試験の短答式の勉強方法は①問題集・過去問集を解く②判例六法にマーク・メモを適宜とる③たくさん間違えた分野のみ基本書を該当箇所読む、です。
①について。私は辰巳法律研究所の肢別本を利用していました。1周目は、とにかく問題をこなすことだけに注力しました。間違えたところは×、正解したけれど解答根拠が明確ではないところ、解説の根拠と違う考えをもっていたところは△、それ以外は○、というふうな感じに印をつけていきました。空き時間(電車に乗っている時間、バイトの休憩時間など)に「○問終わらせる」と目標を立てました。私は過度な目標を立てると続かない性格なので、「最低~問終わらせる」という立て方をせず、「~問終わらせたら強制的にその空き時間での短答式の勉強は終了する」という立て方にしました。2周目以降は、×と△だけを回していきました。
②について。これは2周目以降にしました。間違えた問題の該当条文・関連判例を判例六法にマークしていきました。このようにすることで、後で判例六法だけで総復習することができるようになります(このマーク入り判例六法は、後の口述の条文素読時にも効果を発揮しました)。
③はそのままです。沢山間違えたところ、知識が全体的に曖昧な該当分野だけを、基本書で勉強するという形です(例えば行政法の情報公開分野や、刑事訴訟法の公判前整理手続分野など)。
Ⅳ 論文式試験の勉強法
論文は長い目で継続的に勉強することが大切だと思います。私は主に①大学2年次~②大学3年次~③大学4年次・論文前、の3つの期間に勉強法がわかれます。
①の期間は、法制研究所の下四法入門講座を担当してくださった先生の添削があります。主に憲法を添削してくださいました。1週間に1通程度のペースで自主的に先生に書いた答案を提出し、添削をいただき、その添削をもとに再構成して論文を提出する、といった具合です。当時は、勉強を本格的に開始したばかりで、知識は皆無でした(憲法の3段階審査とは何か、違憲審査基準とは何かが全く分からないというレベルです)。
②の期間は、主に秋からです。それまで予備校を利用していなかったので、何か知識を演習できる予備校教材が必要なのではないかと考えるようになりました。そこで、アガルートの『重要問題習得講座』(いわゆる「重問」。価格は基本7科目セットで10万円程度でした。自分で買える値段だったので、重問にしました)(※以下「演習書」とします)をとりました。「1日3~4問程度あたって考えて、答案構成しよう」と目標を立てました。とにかく沢山の問題にあたるべきという観点から、フル起案せず、答案構成するだけにとどめ、答案構成した後は解答解説を見て、重要部分はマークするといった形で勉強を進めました。
また、大学3年次は法学部と法制研究所が共催している予備試験対策講座をとりました。OBの弁護士先生から直々に論文の書き方や、過去問の分析をしていただけるため、非常に有用でした。ぜひ積極的に取るべきだと思います。特に、先生の予備試験体験談はいくつかあったのですが、その中で「何より事実がとても重要である」というアドバイスは、実際の自分の予備試験に直結しました。たくさんアドバイスをいただける良い機会になるはずなので、受けることをおすすめします。
③の期間は、演習書で見直すべき問題をピックアップしてそれを中心に再度構成するという勉強と、過去問です。前者はそのままの通りで、正確に数えてはいないのですが、4周程度した印象です(ただしフル起案はピックアップしたいくつかの問題しかしていません)。
後者の過去問ですが、次に書く方法はあまりおすすめしない勉強法です。あえて書きますので、あまり真似をしないようにしてください。過去問の問題は法務省の公式から出しているものを出力しました。平成23年の問題から令和5年までの問題です。それを実際に1つ70分(実務基礎は90分)の制限時間で、手書きで解くというものです。猿楽町の空き教室を使い、本番にできるだけ似せた緊張感の中で解きました。問題は、解答解説です。私は予備校の過去問対策講座などとっていなかったため、解答解説をどこから手に入れようか考えました(※ただ、令和分は3年次の予備試験対策ゼミでしっかり解説されているため、ここで問題になっているのは平成分ということになります)。予備校の市販教材は高いため、手を出さなかったです(※手を出した方が良いに決まっています)。そこで、ネットの海に転がっている、どこの馬の骨とも知れない自称A答案、自称模範答案の人の再現答案・解説を読む行為をしていきました。ときどき予備校が、なぜか詳しい解説を一般公開していることもあったので、その時は歓喜したほどです。これだと、誤った知識を吸収する危険が非常に大きいため、金銭的に余裕がなくても、素直に大学教授、OBの先生、予備校の単発講座を利用した方が適切です。
Ⅴ 口述試験の勉強法
口述試験は①参考書を読み知識補充②模試を受ける、の2点です。
①について。参考書は、民事は『完全講義民事裁判実務(要件事実編)』と民法・民事訴訟法の論文で利用した論証集、刑事は『基本刑法Ⅱ』と『刑事実務の定石』と刑事訴訟法の基本書、刑法・刑事訴訟法の論文で利用した論証集を使いました。特に民事は要件事実、刑事は刑法各論と刑訴全般を集中的に見直しました。令和5年度の口述は民事で実体法を中心にきかれていたので、論証集も一応確認しておくべきだと思います。(私の受けた令和6年度は特に実体法はあまりきかれなかったので、やはり要件事実が絶対ですが)。
②について。模試は受けられる分は受けた方が良いです。私は、対面模試は合計5回、zoom模試は1回受けました。知識の確認だけではなく、礼儀作法や緊張感を学べます。
Ⅵ 予備校を活用できない人に向けて
私は、入門・基本講義について予備校は利用しなかったです(費用的な面と、進路変更の可能性もあり、変更した場合に投下した負担を回収できないという面からです)。予備校を利用できる環境にあるならば、当然それは利用した方が良いと思います。以下は、予備校を利用できない人を対象に書きます。
まず、予備校を利用できなくても法科大学院には受かると思いますし、学費免除も十分射程範囲にあります。予備試験合格もしかりです。ただ、以下3点に注意してください。
1つ目は、演習(過去問ではない)は予備校教材(何でも良いです。自分に合ったもの)に頼った方が良いです。私は重問ですが、市販でも沢山分野別に問題が掲載されている書籍があると思います。それは入手して積極的に取り組んだ方が良いと思います。
2つ目は、学内の開講講座は積極的に取った方が良いです。明治大学法曹会が答練を無料で開講しています。全答練に参加せず自分の苦手教科だけをとることも可能です。答案を提出し、先生が直々に添削してくださいます。解説はとても詳細で、自分だけでは学ぶことができないところまで書いてくださっているため、利用すべきです(過去の答練内容もアップされているため、私は過去2年ほどの内容もやりました。なお、余談ですが、その中に民法の失踪宣告分野における双方善意の問題があるのですが、これが令和6年度の予備論文にストレートで出ました。このように網羅的に勉強できるので良いと思います)。
3つ目は、添削してくださる先生は可能な範囲で見つけてください。上記の答練に参加することで添削済み答案を得られるので、その点で参加した方が良いです。既述の予備試験対策講座をとることで、直近5年分の予備過去問を添削・解説してくださいますので、それも積極的に参加するなど、添削してくださる講座を見つけて下さい。明治の開講している講座は基本的に無料だと思うので、費用的には全く問題無いと思います。
Ⅶ 振り返って
まだ司法試験本試験があるため、継続的に勉強していかなければいけないなと、緩んだ身を引き締めるつもりで執筆しています。また、執筆している今、司法試験に向けた勉強はどうすれば良いのか、悩んでいます。
予備試験は確かに難しい試験ですし、人生がかかっています。そのため、他の学部生とは比較にならないほど勉強することは当然です。しかし、せっかくの貴重な大学4年間ですので、勉強だけに全振りすることは少し疑問です。友人、知人との交際やサークル活動、バイト、旅行、読書、その他自己啓発など勉強以外のことも取り組むことも必要なのではないかと思います。加えて、受かれば嬉しいですが、同時に新しい問題も出てきます(論文合格すれば口述、口述合格しても次の司法試験や就職活動など)。結局通過点にすぎないので、「人生がかかっている」と書きましたが、あまり気負う必要はないと思います。
以上