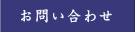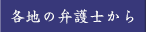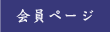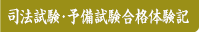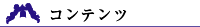明治大学法曹会 予備試験合格体験記
関川桃奈
2024年 明治大学法学部法律学科 卒業
1 経歴
2020年3月 新潟県立新潟南高等学校 卒業
2020年4月 明治大学法学部法律学科 入学
2022年 令和4年予備試験 短答不合格(130点、6080位)
2023年 令和5年予備試験 短答合格(188点、780位) 論文不合格(203.88点、1292位)
2024年3月 明治大学法学部法律学科 卒業
2024年4月 慶應義塾大学法科大学院(既修コース) 入学
2025年2月 令和6年予備試験最終合格(短答:183点、1020位 論文:261.12点、244位 口述:121点、92位)
2 予備試験志望の動機
私は、小学生の頃にリーガル・ハイという弁護士もののドラマを見てから弁護士になりたいと思っていました。それから漠然と法学部に入れば弁護士になれると思い、明治大学法学部に進学しました。大学に入学してから、予備試験に合格するか法科大学院に進学しなければ司法試験を受けることができないということを知ったのですが、予備試験の合格率が4%程度しかないため予備試験合格を目指す決心がなかなかできずに過ごしてしまいました。コロナの影響で学校が始まらなかったり、オンライン授業が続いたりして法律の勉強をあまりせずにだらだら過ごしていたのですが、学部2年の9月頃にこのままではまずいと思い、ようやく予備試験合格を目指す覚悟が決まりました。
3 予備試験短答式の勉強方法
私は7科目全て短答パーフェクト(短パフェ)をやりました。「短パフェはオーバーワーク」「合格セレクションで足りる」との意見もありますが、個人的には時間のある学生は短パフェを周回するのが良いのではないかと思います。私は一般教養科目で点をとる自信がなかったため、法律科目で確実にボーダーに乗る必要がありました。そうでなければ一般教養ガチャという運に左右されて合否が決まってしまうため、予備試験と司法試験の過去問が全て掲載されている短パフェを使った方が安心だと思いました。
ただ、その分短パフェはとても分厚く、問題数がたくさんあるため周回するのが大変です。私は令和4年度の短答受験時(学部3年次)は短パフェを全科目1周することすらできておらず、結果は大差落ちでした。計画的にコツコツ周回する必要があります。令和5年度では、全科目5周することを目標にしていたのですが、実際には2〜3周しかできませんでした。令和5年度は、法科大学院の入試に向けた論文対策に力を入れる必要があったため、短答の比重がどうしても下がってしまったのです。それでも私が短答に合格できたのは、短答対策のコツをつかんだからです。具体的には、1周目2周目は全問やって、間違えた問題には❌をつけ、消去法で正解はしたけど難しい問題や自信のない問題には⭐️マークをつけ、なんとなくわかるけどもう1回やっておきたいという問題には♡マークをつけます。問題を解く際には必ず条文を引いて、赤ペンで六法に書き込んだりマークしたりします。そして、試験の1週間〜2週間前から上記しるしをつけた問題の解説部分だけを高速に読み、頭に叩き込みます。このときは、時間的に余裕がなかったためいちいち六法を開かなかったです。そのため科目によっては1日で1周できます。私がこのようなスケジュールになったのは短パフェの量が思ったよりも多かったためであり、可能であればもう少し余裕を持って進めていったほうが良いと思います。ただ、直前期に高速周回したことで一気に各科目の整理ができたため、直前期の詰め込みは本当に大事だと思います。
令和6年度では、ロースクールの期末試験の1週間前に短答式試験だったため、授業の予習復習・論文対策と短答対策の両立がハードでした。もっとも、前年度に短答式試験は余裕を持って合格していたため、あまり不安はなかったです。ただ、来年は在学中受験ができるため予備試験を受けるのは最後だったので、絶対に落ちられないという気持ちでした。具体的な勉強方法は、1周目は全問やって、2周目は上記しるしがついている問題の中でも引っかかりやすいところや紛らわしいところをできる限り厳選してスマホのメモアプリに科目ごとに書いて整理したり短パフェの解説部分から引用したりしました。そして、試験当日の移動時間や試験の空き時間にそのメモを一気に読んで頭の整理をしました。公法系の直前にはメモアプリの憲法と行政法のメモを読み、民事系の直前には民法と商法と民訴のメモを読むという感じです。試験室では電子機器を使うことができないため、廊下に出て、休憩時間のギリギリまで上記まとめメモを読みました。私にとってはこの勉強方法が一番効率的で効果的だったと感じています。短答は膨大な問題をいかに記憶しているかが大事であるため、短期記憶ではありますが、上記メモアプリにまとめておいて直前に一気に頭に入れるという勉強方法はおすすめです。メモアプリにまとめるといっても、だらだら書くのではなく、復習しやすいように単語レベルや短パフェ解説部分の切り抜き程度で十分だと思います。この勉強方法は伝えにくいのですが、本当におすすめですので是非やってみてください!
一般教養は対策が困難であるため一切しませんでした。法律科目でできるだけ得点し、一般教養科目はおまけ程度に点がもらえたらいいなという感じでした。実際、法律科目165点、一般教養科目18点で、その年のボーダーである165点を法律科目だけでとることができたので、上記勉強方法で良いのではないかと思います。
4 予備試験論文式の勉強方法
私は予備試験の勉強を始めて3年ほどで合格したため、遠回りの勉強や無駄な作業をたくさんしてしまいました。そのため私の論文対策はあまり王道ではなく、おすすめはしません。以下の勉強方法は私の失敗談でもあり、あくまでも一個人の体験記にすぎないのでご注意ください。
まず、学部2年の4月から法政研究所の7科目の入門講座(7万円ほどの)を受講しました。受けてみての感想としては、上記講座の憲民刑は全くおすすめしませんが、下4科目はとてもわかりやすく、全体像を掴むことができたと思います。
明治大学法曹会の予備試験答練(無料)の存在は学部1年のときから知っており、zoomで講師の先生が「最初はみんな書けないけど書いて添削してもらううちにだんだん書けるようになる。」とおっしゃっていたのですが、実際全く書けなくて添削してもらうレベルにも達していないのにどうすればいいんだと悩み、答練を活用することができませんでした。
次に、趣旨規範ハンドブックという辰巳法律研究所の論証集を購入するとともに、スタンダード論文答練(スタ論)を受講しました。法政研究所に所属していると、短パフェやスタ論などを割引で購入できます。前述のとおり答案を書くことができるレベルではないため、何も見ずに答案を書いて提出するということができず、最初のうちは趣旨規範ハンドブックを見ながら時間無制限で書いて、当てはめの部分は自分で考えて書くという作業をしていました。しかし、趣旨規範ハンドブックは簡単な記載にとどまっており、加筆修正して利用することが前提となっている論証集です。そのため、趣旨規範ハンドブックを見ながら答案を書くことも難しかったです。また、答案を書くことに加えて解説講義を聞いて、参考答案を分析し、趣旨規範ハンドブックに加筆修正していくという作業も慣れないうちは非常に大変です。そのため早々に答案を書くことをやめ、問題文を読んで少し考えたらすぐに解説講義を聞き、参考答案を分析してから趣旨規範ハンドブックに加筆修正するという作業をしました。学部2年は専らこのような勉強をしていました。
学部3年では、アガルートの重要問題集(重問)と予備試験過去問講座を単品で購入し、特に重問をベースに勉強しました。重問に載っている問題を見ても何を書けばいいか全く分からなかったので、上記と同様にすぐに解説講義を聞き、参考答案を分析してから趣旨規範ハンドブックに加筆修正するという作業を7科目しました。しかし、ここにきて私には趣旨規範ハンドブックは合わないことに気づき、公法系以外の論証集をアガルートの論証集(市販)に買い替えました。そのため、約1年続けた趣旨規範ハンドブックの加筆修正作業は全くもって無駄でした。個人的にはアガルートの論証集に加筆修正するのが合っていました。その後、予備試験過去問講座も同じように進めていきました。この時点で重問も過去問もほとんど起案したことはなく、答案構成しただけです。答案を書く力はありませんでした。
それからロー入試までは、とにかく重問を使って論点抽出力を養いました。論点がわからなければ論証を覚えてもその論証を貼り付ける場所がわからず、意味がないからです。また、論証暗記は本当に苦痛であるため、それから逃げるために代わりに答案構成をし続けたという理由もあります。私は令和5年の予備試験短答(学部4年の7月)を受けるまで論証暗記から逃げ続け、論証を覚えていないため答案を書くこともできませんでした。しかし、ロー入試1ヶ月前になり、さすがに論証暗記しなければやばいと思い、アガルートの論証集を1ヶ月で死ぬ気で覚えました。この時点でアガルートの論証集を全部覚えていたわけではないのですが、できる限り覚えました。実際に論証集を見ずに答案を書いたことはロー入試本番くらいしかないですが、重問を使って論点抽出力を養っていたため、論証を覚えさえすればある程度のことは書けるようになっていました。そのため、ロー入試も乗り切ることができました。
もっとも、このような付け焼き刃では予備試験論文式試験は突破できませんでした。そこで、令和6年の予備試験に向けて、基本書を読んで自分に足りない知識を補ったり、重問の答案構成の精度を上げたりしました。また、そのレベルアップした状態でもう一度過去問の分析をしたり、実務基礎科目の対策として赤本(伊藤塾)を使って勉強したり、(渡辺先生のアガルート労働法5点セットを使って)選択科目を丁寧に勉強したりしました。さらに、ロースクールに入ってから授業の復習をしっかりやったため、ロー入学してから9月の論文までの間にとても成長したと思います。夏休みの8月は、同じロースクールの友達と自主ゼミ(刑訴、実務基礎)を組んで答案を書きました。
このような勉強過程を経て、予備試験に合格することができました。
5 口述試験の勉強方法
民事実務基礎科目は、大島本(要件事実編)を暗記することと過去問を解くことはマストです。要件事実を覚えることは大変ですが、だんだんと覚えられるので信じてください!法曹倫理と執行保全の対策としては、大島本(基礎編)を使いました。また、民法と民訴の論証暗記をできればやった方が安心かと思います。
刑事実務基礎科目は、基本刑法Ⅱ、基本刑訴Ⅰ、過去問はマストだと思います。基本刑訴Ⅰではなく定石本で足りるという意見もありますが、過去問を見る限り定石本では対応できない年度もあるため、基本刑訴Ⅰをやった方が安心かと思います。また、可能であれば基本刑法Ⅰと基本刑訴Ⅱも読んだ方がいいと思いますが、時間的に厳しい場合には刑法と刑訴の論証集を覚えることで乗り切るしかないと思います。法曹倫理の対策としては、定石本を読みました。
過去問は、民事刑事どちらも2周することをおすすめします。1周目は他の合格者と練習し合うか、自分一人で問題を確認する作業をします。私は2回だけ他の合格者とzoomで練習しましたが、それ以外は一人で過去問をやりました。伊藤塾が過去問を送ってくれるのですが、完全解が載っているわけではないため、自分で答えをメモしたり、正解している再現者の解答に線を引いたりしました。こうすることにより、2周目の復習がやりやすかったです。
模試は、伊藤塾の対面模試、L S Tの対面模試、弁護士がnoteで募集しているzoom模試の計3回受けました。
6 おすすめ
今思えば私の論文式試験の勉強方法はとても遠回りでおすすめしません。以下では、私がこうすればよかったと思う論文の勉強方法について述べます。
まず、入門講座はできれば何かしら受けた方がいいと思いますが、マストではないかと思います。また、スタ論などの答練もとらなくてよかったと後悔しています。明治大学法曹会の答練は無料であるため、答案に書き慣れるという意味ではもっと活用すればよかったかと思います。私は論証を見ながら3通ほど書いて提出しました。
私が一番後悔している勉強方法は、初学者段階での論証の加筆修正です。この作業が一番無駄でした。初学者の段階ではまだ論証に修正を加える能力はありません。この作業を初学者がやっても、他の参考答案を見て使えそうな論証を見つけると、同じ論点を何度も加筆修正することとなります。そして論証集がごちゃごちゃし、結局どの論証を使えばいいか混乱します。この作業は勉強した気にはなるのですが、実力のない段階でやるのは時間の無駄です。
なんとなく全体像を掴んだ後は重問や加藤ゼミナールの基礎問を使って答案の書き方を知り、答案構成をしてみて論点抽出力を養いましょう。最初のうちは答案構成すらできませんが、それは当たり前なので気にせずガンガン1周進めます。そして、アガルートの論証集や加藤ゼミナールの総まくり論証集を使って論点を確認します。2周目3周目も答案構成し、参考答案の法的三段論法の大枠や、規範・理由づけ・当てはめの内容を確認し、分析します。このくらいの時期に論証集を暗記しましょう。本当にこれ覚えられるの?と最初のうちは私も思いましたし、とても苦痛な作業なので逃げたくもなるのですが、個人的には天才でもない限り論証暗記は避けては通れないと思います。なるべく早く論証暗記しましょう!!
そして、答案構成に慣れてきたら、この論点の論証はこのくらいにしよう、これにしよう、というようにわかってくるので、このレベルになったら論証加筆修正作業をする意味があるかと思います。決して初学者段階で論証修正作業に逃げてはいけません!!暗記しましよう。暗記から理解に繋がる場面がたくさんあります。
その後は、適宜自分の苦手な分野について基本書を読んだり、ネットで調べたりしましょう。また、個人的には、あまり答案を書かなくても予備試験に合格できると思います。時間内に書く練習はした方がいいですが、過去問全年度フル起案する必要はないと思います。もちろん、時間がある人は全年度書いた方がいいと思いますが、書くことが目的にならないように注意した方がいいです。
おすすめの基本書・参考書等は、事例研究行政法、行政法解釈の技法、行政判例ノート、判例百選、田中会社法、基本刑法、基本刑訴、刑法事例演習教材、大島本(要件事実編・基礎編)です。憲法判例の射程と合格思考憲法と読解民事訴訟法は評判が良いため購入し一読しましたが、一読程度で十分かなという内容でした。
7 終わりに
予備試験の合格率はとても低く、明治大学出身の合格者も少ないため、目指すことに躊躇される方もいるかと思います。私もそうでした。しかし、実際には本気で正しい努力をすれば可能です。6で述べたことは、私が過去の自分に言ってやりたい内容ですので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
以上