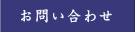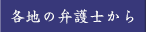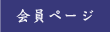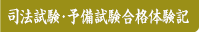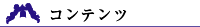明治大学法曹会 司法試験合格体験記
須崎拓人
令和6年 中央大学法科大学院(既習)修了
第 1 略歴・法曹志望の動機
平成 3 0 年 4 月 中央大学法学部法律学科入学
令和 4 年 3 月 中央大学法学部法律学科卒業
令和4 年 4 月 中央大学法科大学院(既習)入学
令和 5 年1 1 月 令和 5 年度司法試験 合格
令和 6 年 3 月 中央大学法科大学院(既習)修了
令和 6 年 5 月 国家公務員試験総合職試験合格
私は高校生の頃、アメリカの弁護士が原作の『依頼人』という映画を見て、 弁護士という仕事に憧れて法学部に進学しました。しかし、入学直後に様々な誘惑に負けて法律に対する情熱が後退してしまいました。それから3 年が経ち大学 4 年生になった頃、自分の進路について考えを巡らし、味方のピンチを救ってくれるかっこいい弁護士に憧れていたことを思い出しました。それから勉強に打ち込むようになり約2年間の学習で司法試験に合格することができました。
第 2 学習方法
学習開始直後から大学院入学を第1期、大学院入学から受験半年前までを第2期、受験半年前から当日までを第3 期として、それぞれの時期の学習方法を振り返ります。
1 第 1 期〈学習開始期~大学院入学〉
コロナ期間により法律学科の友人とも交流が薄くなっていたこと、また大学4年生になった段階で民間就職をやめて大学院進学をしたくなったことを両親に話す勇気もなかったため、完全独学・自己流で学習をスタートしました。
大学院入試まで時間がない中で答案の書き方から覚える必要があったため、市販の論文問題集の解答例をひたすら覚えるという作業をしていました。論文の型を覚えると共に解説を読むことで法律の入門的知識を習得しました。
具体的には、論文問題を読んでみて、どう書くか考えてみます。もちろん知識がないのでほとんど書けません。それで解答例と解説に目を通し、再チャレンジする。それでもまだほとんど書けません。解答例を書き写してみて、再チャレンジしてみる。そうすると少しは書くことができますが、今度は自分の解釈論に対する理解が浅いことに気づきます。そして解説を注意深く読んで再チャレンジします。
このようなプロセスの繰り返しが最初は効きました。合格後に振り返って思うのは諭文問題へのチャレンジは早ければ早いほど良いということです。基本書を読み終えてから起案する方法もあるのかもしれませんが、私だったら問題を解ける喜びを知る前に挫折していたと思います。
2 第2期〈大学院入学後から受験数か月前〉
法科大学院には運よく学費免除で合格することができましたが、変な自信をつけてしまい遠回りしてしまったのが第2期です。
授業の予習に学習時間の大半を費やし、講義で取り扱われる判例は調査官解説を読み、自習席には分厚い本を置き(全部読めるはずがないのですが)、高度な学習ができている自分に満足するようになってしまいました。
大学院入学後しばらくはこの勉強法でも成績は伸びていました。しかし、続けていくうちに、“高度な論証”をしたがる癖がついてきてしましました。採点者に対して、私はこんなことまで検討できているのだ!という顕示欲に取り付かれた答案を書く癖がついてしまったのです。しかし、独自理論を論証するには紙幅と時間を消耗します。作問者は答案に使ってほしい事情を問題文にちりばめていますし、誘導も仕込んでいます。自説にこだわるあまり、これらの事情や誘導に目がいかなくなることは試験対策としては本末転倒です。
3 第 3 期〈受験数か月前から当日〉
受験の数か月前頃に期末試験で刑事訴訟法の答案を独自理論で熱く書いたところ、「必要ない」、「問われてない」など赤を入れられ、私の顔も真っ赤になってしまいました。答案が返却される前には自説の正当性を周囲に熱く語っていたので、得意分野でなかったなどの言い訳はできませんでした。
しかし考えてもみれば、作問者は答案で使ってほしい事情を問題文中にちりばめています。具体的な場面設定において適切な法的処理が考えられているか、結論を導くために必要な解釈論が示されているかを見たいのです。
学習の最終段階は初心に帰り、繰り返し問題を解きました。上位合格者の答案には無駄な論証がなく、問題文の事情を適切に拾い上げて評価できていることもわかりました。そしてそのような答案を作り上げられるようになるためには、やはり繰り返し問題を解いて、解答例・解説を分析し、また人に読んでもらい、おかしい点を指摘してもらうことに尽きるように思います。
第 3 最後に
結果として、私は司法試験に合格することができました。遠回りもしましたが、それも必要な経験だったように思います。現実に生起する法的現象に誘導はありません。司法修習を経て思うのは、遠回りして、ああでもない、こうでもないと考えていた時間が今の自分を支えているということです。
後進に対してアドバイスできることがあるとすれば、法律を楽しむ心と試験対策は両方大事だし、両立できるということです。
司法試験は苦しいですが、乗り越えられない試験ではありません。応援しています。頑張ってください。
以上